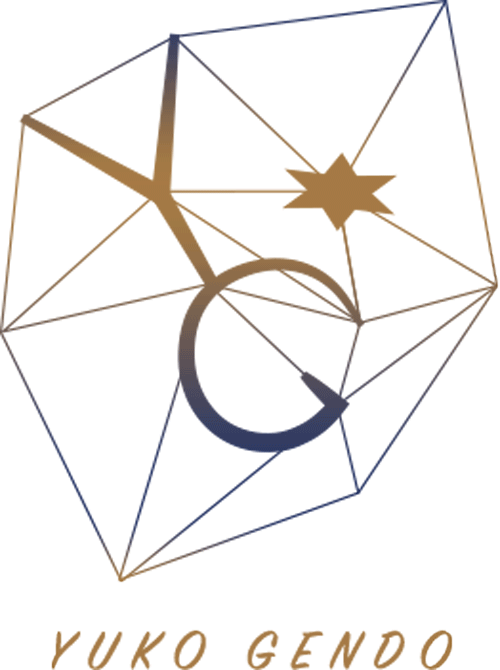オンラインとオフラインの共創の時代へ オンラインボード活用の4つのヒント
2020年6月27日

ワークショップをレベルアップさせたい方へ
オンライン・オフライン連携を作るためのオンラインボード活用のススメ
新型コロナの影響で一気にオンラインの場が広がりました。現在、少しずつオフラインの場も戻ってきているとは思いますが、今後はオンライン、オフラインの組み合わせの場も増えるのではないかと思っています。(現に、私がお仕事させていただいている組織でも初回は対面、合間はオンライン、最後は対面という流れでプログラムが進んでいるケースが出てきています。)
オンラインとオフラインの連携をするためには、
- 全体のプログラムの設計にオンライン上のやりとりを作ること
- ハーベスト(=その場から生み出されるものを記録)の視点を取り入れること
- そのハーベストをオンライン上に残せる仕組みを作ること
の3点が大切。オンライン上に実施した内容や、その感触を残せる仕組みを持っておくことでオフライン、オンラインのつながりを格段に高めることができます。
ちなみにハーベストとは簡単にお伝えすると、話し合いやその場から生まれたもの、を意味します。
話し合いの様子を写真や動画に残す、グラフィックレコーディングで残す、何かのメタファーを使って残すなどいろんな方法があるため、ここでは詳細に書きませんが、その場から生まれたものの事実・感触を含めて拾い上げる視点だと思ってください。 (議事録などの記録もハーベストの一部です)
オンラインのやりとりを生むオンラインボード活用術 4選
ではオンラインボードを活用して、オンラインのやりとりを生むためにはどんな方法があるのでしょうか。具体例を挙げた方が分かりやすいと思うので、実際に私が実施していることのごく一部をご紹介してみます。
自己紹介やコミュニケーション用のボードを作る
すごく簡単で取り入れやすいのは、研修の前、ワークショップの前にコミュニケーションボードを作ること。私は公開ワークショップをするときなどはこれを行うことが多いです。
MuralやMIROを使ってボードを作っておき、その中に主催チームの自己紹介、当日使う資料(あれば)をダウンロードできるようにしておく、注意点などを書いておき、参加する人からも気になっていることや質問があればボードに貼ってもらうようにしています。+自己紹介やチェックインのコメントもお願いすることも。

事前にゆるやかにやりとりが始まっていると、当日も「全く誰も知らない」状態よりは、安心感を持って参加できるのではないでしょうか。
プレセッションボードを活用
1つ目に近いですが、「事前にお題が書かれていてそれに回答しておく」というプレセッションのようなボードを作ることもあります。(&参加者としても体験したことがあります。) 例えば、オンラインのワークショップを効果的に行うためのイベントがあったとします。
この時、事前に「現在オンラインワークショップを実施していて、困っていることは?」とか「自分が実践している中で、『これはおすすめ!』というアイデアを3つ教えてください」などの簡単な問いかけを書いておき、参加者が事前にそのボードに記入をしておくというもの。
当日はオンライン、オフラインどちらであってもそれを皆で見てみながら進め方を決めたりしています。 ツールは同じくMural、MIROまたは簡単に付箋だけを使って実施ならLinoとかもシンプルで良いかもしれません。(ただ、Linoは参加者として使用する場合もID登録が必要だった気がします。)
「オンラインワークショップにおすすめのツール」を投稿してもらう、「オンラインワークショップについて気になる記事をシェアしてもらう」など、イメージやリンクを使って回答してもらうなら、Padletが個人的にはおすすめです。
振り返りのボードを作る
また、振り返りのボードを作るのも特に連続するプログラムの仕事で、最近よく行っています。
例えば、、、下記のようにプログラムの合間に参加者の方に振り返りのボードを書いてもらうようにしたり、

タイムライン形式で実施した内容のまとめを書いていって、全体の振り返りを行ったり、という感じです。

取り入れやすいですし、振り返りをする時間をとってもらうことで、参加者にとっても学びも深まるので研修の振り返りや連続するプログラムの合間に行ってもらうようにしています。
ハーベストボードを作る
実際に当日実施した資料やワークショップで使用した模造紙や付箋をまとめてオンラインボードにアップしたり、終わった後の学び・気付き・感想を参加者に付箋に書いてもらったり、手書きでA4の紙に書いてもらい、それを写真に撮ってアップロードしてもらうこと。
学んだ成果を集約するボードのようなイメージです。 連続プログラムの中で特にキーとなるセッション(最初とか最後とか)では対面で実施した内容のハーベストボードをオンラインに作成し、参加者に送付→参加者にもコメントを書いてもらうようにしています。
オンラインワークショップで使えるツールを知りたい方へ
オンラインボードの作成は対面と違うコミュニケーションが表れる

もちろんツールへの慣れによって差が出ますし、オンラインボードは話すことより書くことが得意な人の方がさっと動く傾向にあるため、対面とは違ったコミュニケーションが表れるのも面白いなと感じています。 対面で表れるやりとりがそのチーム、組織の全てではないはず。オンライン・オフライン両方のやりとりが入るプログラムの方が、参加者の包括的な関わりを感じることができますね。
また、オンラインボードを活用することで参加の粒度に差をつけて場をデザインすることもできるようになります。 例えば、対面のワークショップにはチームの代表者が集まって参加するけど、その一部の内容は参加者がチームメンバーにオンラインボードを使って意見をもらってくる、など。 まだまだ探求の余地がありそうですね。
ツールを気軽に取り入れられるかはその組織の行き先を左右する!?
「こういうツールや方法を取り入れてみませんか?」と提案をしたときにさっと「面白そうですね!やってみたいです」という組織と、「いや、うちではセキュリティが厳しいのでちょっと…」と尻込みする組織と分かれる傾向にあります。オンライン化が進むにつれ、ツールや方法などこれまでと違ったことをさっと選べるかどうかは組織の行き先を左右するのではないでしょうか。
私自身、自粛期間中はかなり研究と実践を重ねたので、それを活かして近いうちに上記のツールや方法を取り入れたオープンイノベーションの実験をしたいと思っています。 またお知らせできる段階になりましたら、このブログでもご案内させてください。
上記のようなオンラインツールを活用したオンラインワークショップを開発したい、相談したい方はぜひお問い合わせからどうぞ!
オンラインのワークショップのコツについて知りたい方はこちらの記事もどうぞ。